レンガ造りの架道橋(広島県呉市)
3週間ほど前のことになりますが、5月10日は呉線に残るレンガ造りの架道橋を訪れました。

魚見山隧道手前の架道橋を見て思い出す
呉線の川原石駅から吉浦駅の区間、魚見山隧道まわりに呉線敷設当時の架道橋が3本残っていることは知っていたのですが、正確な場所は知りませんでした。そして、いつの頃からか架道橋の存在はずっと記憶の外でした。しかし、少し前に川原石側から魚見山隧道に入るところで架道橋を発見。

以前は架道橋手前に建物があったのですが、撤去されて見えるようになったようです。架道橋の記憶が蘇りましたよ(笑)。私に記憶を蘇らせてくれたこの架道橋は水ヶ迫川橋梁です。幅3.05m、長さ18.5mで水路として使われています。
なぜ架道"橋"なの?
ところで私、なぜ"架道橋"というのかずっと疑問でした。"橋というよりトンネルじゃん"という感じ。そこでGeminiさんに「鉄道においては線路の下のトンネルも架道橋というのですか?」と質問してみました。頂いた回答がこちら。
はい、鉄道において線路の下を道路などが通る場合、その構造物も「架道橋」の一種とされます、
Google Geminiさん
一般的に「橋」と聞くと、川や谷を跨ぐものを想像しがちですが、鉄道用語における架道橋は、鉄道が何か(道路、河川、他の線路など)を跨ぐ場合だけでなく、鉄道の下を何かが通過する場合の構造物も指します。
–略–
ご質問の「線路の下のトンネル」という表現ですが、もしそれが比較的短い距離で、明確に「橋」としての構造を持っている場合は「架道橋」と呼ぶことが適切です。山を貫くような長大なトンネルとは区別されるのが一般的です。
–以下略–
Geminiさん、ありがとう(^-^)。そっか、生成AIというのは、こういうことに使うんだなと(違う)。
話を架道橋に戻します(汗)
エンジニアの端くれ(?)として"生成AIなるものを使ってみたこと"を記したかったのですが、話を元に戻します(爆)。水ヶ迫川橋梁を確認して、他の架道橋を確認するために出かけたのが5月10日だったのです。予習はしてでかけたので、コインパーキングにC3をとめることもできました(^-^)。川原石駅から架道橋を求めて歩きます。
3つの架道橋のうち、川原石駅から最も近いのが第四川原石橋梁です。このページの最初の写真も第四川原石橋梁です。

海側から覗いてみました。高さも幅もホントに小さい。背の高い人だとかがまないといけないかも。幅1.83mしかありません。長さは17.01mです。

山側からみるとこんな感じ。
次にたどり着くのが私に架道橋の存在を思い出させてくれた魚見山隧道近くにある水ヶ迫川橋梁です。そしてもう少し歩くと新宮川橋梁があります。

今日も"ピクミンブルームで花植えをしたい"ということでついてきたツマ。"今日もへんなところにやってきてるな"と感じていたのでしょうが、橋梁内部を歩いたりしていたので、きっと楽しんでくれたに違いありません(^^(^^;。

新宮川橋梁は幅が2.44m(ちなみに長さは28.35m)あるのですが、通路と水路があります。第四川原石橋梁も水路があるのですが、暗渠になっています。新宮川橋梁は暗渠になっていないため、通路部分が第四川原石橋梁よりも狭く、人がすれ違うのも気を使います。
そして水路があるためでしょう、フナムシらしき虫がたくさんいました。フナムシ… 久しぶりに見ましたよ(^^;。

現在の川原石駅下にも以前はレンガ造りの架道橋(西の谷川橋梁)がありましたが、は昭和57年にボックスカルバートに変更されました。
呉市のホームページによると、第四川原石橋梁、新宮川橋梁ともに現在も生活道として使われているそうです。これだけ狭いと不便もありそうですが、活躍を続けて欲しいですね。
参考にした書籍など
- 街の色はレンガ色 ─呉レンガ考─ 呉レンガ建造物研究会編 / 中国新聞社





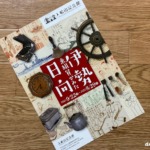






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません